2024年09月05日
WW2ユーゴ紛争ヒストリカルゲーム「ボスニア194X」【枢軸軍(ドイツ)の装備について④】
枢軸軍(ドイツ)の戦闘装備について。
枢軸軍は守備と哨戒が主な任務となります。
軽装備を想定してください。
基本的に、日本国内や海外で入手できるレプリカや代用品であれば使用に問題ありません。
各装備品については極端に破損(破れたり折れたり)しやすい素材や品質でなければ、何処のメーカーでも問題ありません。
ただし、明らかに形状が異なっている装備や代用品に関しては主催の判断で、当日は使用ができなくなる場合もありますのでご了承ください。
以下は推奨装備です。これらが無くても基本的に参加可能です。


各重装備用Yストラップ。革製前期型/後期型、ウェブ製熱帯地方用、軽装用/非軍事組織用等、これらが無くても参加は可能です。必須装備程度であれば、戦闘服のベルトフックを使用すれば問題ありません。

ガスマスク及びケース。無くても基本的には問題ありません。


国防軍/武装親衛隊用ポンチョ。無くても問題ありません。

携行ショベル。無くても問題ありません。



飯盒。こちらは状況中は不要ですが、フィールド提供の昼食時に使用できます。
参考元:AT THE FRONT
枢軸軍は守備と哨戒が主な任務となります。
軽装備を想定してください。
基本的に、日本国内や海外で入手できるレプリカや代用品であれば使用に問題ありません。
各装備品については極端に破損(破れたり折れたり)しやすい素材や品質でなければ、何処のメーカーでも問題ありません。
ただし、明らかに形状が異なっている装備や代用品に関しては主催の判断で、当日は使用ができなくなる場合もありますのでご了承ください。
以下は推奨装備です。これらが無くても基本的に参加可能です。


各重装備用Yストラップ。革製前期型/後期型、ウェブ製熱帯地方用、軽装用/非軍事組織用等、これらが無くても参加は可能です。必須装備程度であれば、戦闘服のベルトフックを使用すれば問題ありません。

ガスマスク及びケース。無くても基本的には問題ありません。

国防軍/武装親衛隊用ポンチョ。無くても問題ありません。

携行ショベル。無くても問題ありません。



飯盒。こちらは状況中は不要ですが、フィールド提供の昼食時に使用できます。
参考元:AT THE FRONT
2024年09月05日
WW2ユーゴ紛争ヒストリカルゲーム「ボスニア194X」【枢軸軍(ドイツ)の装備について③】

枢軸軍(ドイツ)の戦闘装備について。
枢軸軍は守備と哨戒が主な任務となります。
軽装備を想定してください。
基本的に、日本国内や海外で入手できるレプリカや代用品であれば使用に問題ありません。
各装備品については極端に破損(破れたり折れたり)しやすい素材や品質でなければ、何処のメーカーでも問題ありません。
ただし、明らかに形状が異なっている装備や代用品に関しては主催の判断で、当日は使用ができなくなる場合もありますのでご了承ください。
以下は基本的な必須装備です。

装備ベルト・銃剣・雑嚢・水筒



装備ベルトは革製を推奨します。

バックルを忘れないように気をつけてください。アルミ・スチール・ニッケル・真鍮等の素材、革タブと塗装有無の何れも使用可能です。

銃剣は状況中の着剣を禁止します。
主催が安全を確認して、許可を得た場合の写真撮影等は問題ありません。※銃剣は合法品のみ持ち込み可。

雑のうと水筒は必須です。


M31雑嚢/Brotbeutel31。

各ストラップ類がウェブ製の熱帯地方用と呼ばれている仕様でも問題ありません。雑のう内の入組品は各参加者の判断とします。中身が空の場合はタオル等を入れてください。

雑嚢用ストラップは工夫次第で応用が出来ます。所有していれば持ってきてください。



M31水筒/Feldflasche31。0.8/1.0リットル型の何れも使用可能です。実用したくない場合は雑嚢内に飲料水ボトル等を入れて、水筒カップに注いで使用してください。

これらの基本装備に使用する各弾薬ポウチを縛着してください。


先に紹介した雑嚢用ストラップで弾薬ポウチを吊り上げても良いでしょう。
これらの装備品は、だいたいのリプロダクトでも問題ありません。
前述した通り、明らかに形状が異なっている装備や代用品は使用が出来ません。

このようなリプロダクトは使用不可です。
装備について不安がある場合は主催までお気軽に問い合わせください。
2024年09月01日
ラドムVIS wz1935 ホルスター/チェコ製リプロダクト

ラドム拳銃(P35)の存在は知っていたものの、ドイツ軍用として広く使用されていたのを認識したのは割りと最近でした。


Walther PPホルスターを購入したチェコのベンダーから製品化されていたので、入手してみました。


同社のPPホルスター。非常にカチッとした仕上がりでギボシ金具もアルミ製。
ここが真鍮製だと萎える…インドやパキスタン製は真鍮製なんだよな。

P35とシルエットが似たM1911A1が入るかな?と思いきや、モデルガンもガスガンも入らなかったです。
P35は製造工場をオーストリア(オストマルク)に移転して、最終的には30万挺も生産されたとか。

その多くは武装親衛隊や空軍向けに支給されたようです。
こちらは武装親衛隊500降下大隊の装備を組んでみた状態。
基本的に全てリプロダクトです。

みんな大好き「戦略大作戦」ではM1911A1の代役としてP35が使用されていたとか。
撮影地のユーゴスラビアには、それなり数量が遺されていたんでしょうかね。
参考:Internet Movie Firearms Database
2024年08月29日
21世紀の扉を開く

6月2日に開催されたイベント、Operation Tropic OceanV3[アジア周辺地域装備ミーティング]に参加しました。
持参したのは靴と下着とトラウザーズベルトのみ、あとは先輩と友人からの借り物を借用させて頂きました…



超最先端な装備を着用して悦に入る、中の人…
スゲー!何かイロイロと最先端だぜ!とはしゃいでいる様子…
あんまりにも楽しかったので…
当日に借用した帽子と戦闘服上下を半ば強引に買い取り、21世紀の扉をコジ開けてしまいました。

先ずは各記章類。
部隊は思い入れのある3RAR(オーストラリア歩兵連隊3大隊)を目標として、ナショナルフラッグパッチ(国章)とユニットパッチ(部隊章)2種を入手。

こんなスタイルで落ち着きたいところ…迷彩服でスロウチハット、狂おしいほど格好いい…



ランクスライド(階級章)とネームテープ(名札)とスローチハット用ユニットパッチを追加。ライジングサンバッチは幸いにして、使用出来る年代のモノを持っていました。

ギッグルハット(ブッシュハット)とシャツと靴下、トラウザーズベルトとランクスライドと各パッチ等、全てCADET向けPX販売品です。官給品ではありません。


こちらもPX品。

A4サイズの書類やファイル入れ…キミ、100均で見かけたことがあるなぁ…


こういうの好きなので買ってしまった…



メモ帳。巻末はカーボン紙がついてる。


各種規範を管理出来るファイル…
各種規範は検索すればDL出来ます。本当に便利な時代。
現役先任下士官なのか士官学校生徒を再現するつもりなのか、かなり迷走気味ですな。
ここまでノンビリ始めて約2ヶ月ぐらい経過。




ブーツの選択肢が多くて、かなり悩みました。
個人的に履きやすいと思っているのはDannerなんだよなぁ…
気分転換と見切り発車でスタートした21世紀装備の道も、やはり永く険しい…闘いは果てしなく続く。
2024年08月29日
ドイツ軍ヘルメット擬装網の続き。

前回の続き…やはり網自体が大きいです。
大は小を兼ねる、てことなんでしょうかね。
いまいち、取り付け方法がイメージ出来なかったんですが、現在は検索すればあれこれ出てきます。さすが21世紀!
実物(と言われているモノ)の画像を眺めていると、麻紐の色味も気になってきました…
リプロダクトは生成りの色味。実物はもう少しばかり濃い色味です。経年による変化も多少はあるんでしょうが。
※いわゆる時代漬けの影響も…

週末に作業するつもりでしたが、気になったので…
紅茶で煮しめてみました。だいぶ縮んで、面倒なサイズ調整も不要になったかも?


画像を参考にしてヘルメットライナー側にもフックを追加。

M38ヘルメットはライナー形状が特殊ですが、こんな感じ?


ヘルメットに被せてみました。
フェイスベールになる部分は後方にまわして、フックで固定しています。


やはり参考画像と比べると大きい?

でも全軍共通型のヘルメットならば丁度良いかも。
余った網部分はヘルメット内側に巻き込む場合もあるようです。
ヘルメットの思わぬ反射を防ぎつつ、頭から肩への輪郭をぼかすことで擬装の効果は上がります。
日本陸軍のような擬装網と構造は簡略化されているので、自作も簡単かも。
参考:WARHATS.COM :WW2 German Helmet Camouflage Nets
2024年08月27日
ドイツ軍ヘルメット擬装網

もう買い物しないと言ったな、あれはウソだ…
今はこんなアイテムもリプロダクトがあるんですね。


降下猟兵や空軍地上部隊での使用例が多く見られる、ヘルメット擬装網のリプロダクトです。
こんなん自作できるじゃん、みたいなアイテムですが、寄る年波はモチベーションとかを下げるんですよ…
実際のところ、これは支給品ではなくて官報とかに紹介された自活品なんじゃないでしょうか。※工事生産という記述もあるっちゃあります


こちらは実物として紹介されています…こんなの怖くて買えません。
構造はいたって簡単。
網にヘルメット外周固定用に紐を通して、リングとフックを付けるだけ。

ヘルメットライナー前後に針金でフックを作って、擬装網を固定しておしまい。


この擬装網が少し面白いのは、顔面部分も覆えるようになっているところでしょうか。
普段は擬装網の角部分に付けられたフックで、後方に固定できるようになっています。

さて、こちらがリプロダクトです。
ヘルメット外周固定用の紐が微妙にズレてる。
ちょっと紐をほどいて位置調整が必要かしら…
少しデカい気もする。頑張れば2つ分いけるかも?

まあ、あまり慌てても仕方ないので週末にでも作業します。
2024年08月01日
『DANGER CLOSE 196X』Ver.4 参加ユニット概要1
『DANGER CLOSE 196X』Ver.4 参加ユニットについて。
南側は以下のユニットが参加できます。




ベトナム共和国陸軍憲兵隊/ベトナム共和国国家警察
アメリカ陸軍憲兵隊/アメリカ空軍基地警備隊/各国軍事援助部隊憲兵隊

アメリカ海兵隊保安警護隊(大使館警備)
憲兵隊/基地警備隊/海兵隊/現地警察については、午前中も銃を携帯可能です。
ただしBB弾の装填とパワーソースを充填してはなりません。
安全管理はフィールド内に入る前に徹底します。
必ずご協力ください。
憲兵隊/基地警備隊/現地警察の任務について。
・市内の治安維持、風紀の乱れを正すこと。
憲兵隊/基地警備隊/現地警察の装備について。
・拳銃・小銃・短機関銃まで。※BB弾は支給制です
海兵隊保安警護隊の任務について。
・アメリカ大使及び施設の警護。
海兵隊保安警護隊の装備について。
・拳銃・小銃・短機関銃・軽機関銃まで。※BB弾は支給制です
各員は選抜されたエリートであることを意識してください。
被服や装備は実物である必要はありません。
ただし適切な状態で参加に臨んでください。
状況開始前に装備点検を行います。
南側は以下のユニットが参加できます。




ベトナム共和国陸軍憲兵隊/ベトナム共和国国家警察
アメリカ陸軍憲兵隊/アメリカ空軍基地警備隊/各国軍事援助部隊憲兵隊

アメリカ海兵隊保安警護隊(大使館警備)
憲兵隊/基地警備隊/海兵隊/現地警察については、午前中も銃を携帯可能です。
ただしBB弾の装填とパワーソースを充填してはなりません。
安全管理はフィールド内に入る前に徹底します。
必ずご協力ください。
憲兵隊/基地警備隊/現地警察の任務について。
・市内の治安維持、風紀の乱れを正すこと。
憲兵隊/基地警備隊/現地警察の装備について。
・拳銃・小銃・短機関銃まで。※BB弾は支給制です
海兵隊保安警護隊の任務について。
・アメリカ大使及び施設の警護。
海兵隊保安警護隊の装備について。
・拳銃・小銃・短機関銃・軽機関銃まで。※BB弾は支給制です
各員は選抜されたエリートであることを意識してください。
被服や装備は実物である必要はありません。
ただし適切な状態で参加に臨んでください。
状況開始前に装備点検を行います。
2023年05月02日
ベトナム派遣オーストラリア軍について②

~オーストラリア陸軍 第3歩兵大隊 第2次ベトナム派遣~
東南アジア条約機構(SEATO)の主要構成国であるオーストラリアは、1962 年より軍事顧問団のベトナムへの派遣を開始しました。
1965 年からは大規模な兵力の派遣を行っています。
ここではオーストラリア陸軍 第3歩兵大隊 (3rd Battalion, The Royal AustralianRegiment)の第 2 次ベトナム派遣(2nd Tour)について簡単に説明してみます。
1970 年、ニクソン大統領によるベトナミゼーションが開始され、アメリカ軍とオーストラリアを含む同盟国軍も段階的な撤退を開始していました。
第3歩兵大隊の第 2 次派遣は 1971 年 2 月から同年 10 月までの 8 ヶ月間、再びフォクトゥイ省ヌイ・ダットに駐屯を開始。
共産軍は戦力が減少した隙に乗じて、支配地域の拡大を図って戦闘は一部で激化。
第3歩兵大隊もロンカンの戦いと呼ばれる大規模掃討作戦に従事しました。

第3歩兵大隊B中隊5小隊の集合写真。
ロンカンの戦い
1971 年 6 月 6 日に実行された『オーバーロード作戦』に呼応して、第1オーストラリア統合任務部隊(1ATF)は、ロンカン省に存在している
南ベトナム解放民族戦線(NLF)D445 機動大隊及びベトナム人民軍第33連隊のベースキャンプを撃滅すべく、大規模掃討作戦を実行しました。
センチュリオン戦車を含む機甲部隊、砲兵部隊による支援砲撃も行われ、第3歩兵大隊とニュージーランド兵を含めた第4歩兵大隊による侵攻が開始されました。
しかし、事前に大規模作戦の予兆を感じていた D445 と33連隊による徹底的な防御戦闘と、巧みに配置された阻止陣地の頑強な抵抗を受け、侵攻は停滞していきました。
オーストラリア歩兵部隊への弾薬補給に投入されたヘリコプターも、北側に撃墜されるほどの激しい戦闘が続き、やがてセンチュリオン戦車の突入により北側の陣地も次々に陥落。 ロンカン省の共産軍ベースキャンプ掃討作戦は当初の目標を達成しました。
しかし D445 大隊と第33連隊の兵士は人員の大半が戦闘地帯からの脱出に成功しています。
1971 年10月6日、最後の第3歩兵大隊兵士が同地より離れ、祖国へと帰還しました。
M1956 歩兵戦闘装備の改善要求
オーストラリア軍は、アメリカ陸軍の M1956 歩兵戦闘装備を採用していました。当時の水準として先進的な M1956 歩兵戦闘装備ではありますが、戦地で使用されるうちに欠点も見られるようになりました。
マガジンポーチは L1A1 弾倉を各 2 本のみ収納可能、シュラフ/寝具はクイックリリース可能なウェブストラップでサスペンダーに固定するようになっていましたが、密林内での携行性は悪く、また木の枝などでズタズタになってしまいました。 堅牢な M1956 歩兵戦闘装備ではありましたが、過酷な戦場での消耗も著しく、前線の兵士たちからの改善を求める声が多数あがったと考えています。
オーストラリア M1956 歩兵戦闘装備について



前線の兵士たちからの改善要求に対して開発されたのが、オーストラリアが自国製造したM1956 歩兵戦闘装備です。マガジンポーチは L1A1 弾倉を最大で 4 本収納可能、これまで使用されていた P37 ラージパックに代わる新型ラージパック、ワイヤーフックと ALICE クリップを備えた水筒、新素材を使用した H 型サスペンダー、容量の増えたキドニーポーチが開発されました。


マガジンポーチは大型化され弾倉の収納数は増えましたが、引き続きポーチ内には手榴弾を収納し予備弾薬クリップはバンダリアで携行せよ、と統制された部隊もあったようです。



新型ラージパックは上下 2 層に分かれており、上層には携帯口糧等を、下層には寝具を収納する構造になっています。ショルダーストラップはクイックリリース機能が備えられています。
水筒は 2 通りの装備ベルトへの縛着方法が選択可能ですが、ワイヤーフックは引っ掛かりやすく専ら ALICE クリップでの使用が好まれていたようです。
ベトナム派遣オーストラリア軍の新型戦闘服



これまで使用されていたジャングルグリーンシャツとクロスオーバーベルト型のトラウザースに代わり、より実戦向けの戦闘服も導入されました。Pixi シャツと呼ばれるジャングルグリーンシャツとトラウザースが正式導入された時期は、残念ながら分かっていません。Pixi シャツは胸ポケットが大型化され、両上腕部にはポケットが追加され個人用包帯等が携帯できます。又、着丈も短いのでシャツをトラウザースに託しこまずに着用することができます。

1枚襟で袖部分に補強がある1型、2枚襟で袖部分の補強が省略された2型、2型とほぼ形状も同一なるも生地が薄手の木綿になった3型を確認しています。


トラウザースの大腿部正面には大型ポケットがありますが尻部ポケットはオミットされました。腰にはアジャスターが付いています。トラウザースに関してもポケットの仕様に差異が複数あるようですが、これらは製造メーカーによる仕様違いなのか分かっていません。
ベトナム派遣オーストラリア軍についての四方山話②
2021 年に日本国内でもロンタンの闘いを描いた戦争映画『デンジャー・クロース 極限着弾』が公開されました。現地のリエナクターや当時のベテランも作品に参加、当時の戦況を分かりやすく描写しつつも、劇映画としても楽しめる内容となっています。
気になる戦闘服や装備品については、レプリカも使用されているようですが、設定であるところの 1966 年を再現すべく、なかなか見どころの多い表現が為されています。
戦争映画なので、残念ながら日本語字幕に関しては省略や間違いが見受けられます。 情報量の多い日本語吹き替え版で観賞すると、より作品の内容が楽しめると思います。
日本国内のインターネットオークション等で流通している、いわゆる「ナム戦オーストラリア軍装備」は、1980 年代の同型品が多いようです。残念ながら識別点が分かりにくいので、日本国内のみならず海外でも「ナム戦当時モノ」として流通しているのが現状です。
オーストラリア M1956 装備は、ベトナムから撤退後も若干の仕様変更を行いつつ使用されていたので、程度が良い状態のモノは少なくなっています。
残念ながらアメリカ軍 M1956 装備のようにリプロが販売されることは恐らくないでしょう。
個人的には、先ずは戦後同型品を足掛かりにして装備を組んで、ヒストリカルゲームイベントに参加してみるのは悪くないと思います。
自分も初めて参加したアホカリ VN は全て1980年代の同型品からスタートしました。
現在ならば遠回りすることなく、もっと再現度の高い装備が集められるのではないかな?と思います。
先ずは参加して、他の参加者の装備や被服を見せてもらったり、分からないことは臆せず質問すれば、100%ではないですが何らかの回答があるはずです。
一番怖いのは「分かったつもり」になって、完全に間違えたままで続けてしまうことです。 そんなわけで、ベトナム派遣オーストラリア軍について少しでも興味があった場合は、恐れることなくイベントで声をかけてみてください。
出典:Australian War Memorial
Battle of Long Khánh
2023年04月28日
ベトナム派遣オーストラリア軍について①

~オーストラリア陸軍 第3歩兵大隊 第1次ベトナム派遣~

東南アジア条約機構(SEATO)の主要構成国であるオーストラリアは、1962年より軍事顧問団のベトナムへの派遣を開始しました。
1965年からは大規模な兵力の派遣を行っています。
ここではオーストラリア陸軍 第3歩兵大隊(3rd Battalion, The Royal Australian Regiment以下3RAR)の第1次ベトナム派遣(1st Tour)について簡単に説明してみます。
3RARの第1次派遣は1967年末から1968年末までの1年間に渉り、フォクトゥイ省ヌイ・ダットに駐屯を開始。
1968年のテト攻勢ではアメリカ空軍ビエンホア空軍基地に対して増援部隊を送っています。
3RARはその後も複数の作戦に参加し、地雷除去、対迫撃砲戦闘や偵察任務に従事しました。
1968年末、3RARは第9歩兵大隊(9RAR)と任務を交代、祖国へと帰還しました。
第1次ベトナム派遣では3RARは24名の死亡者、93名の負傷者を生じています。
彼らは連隊共通のモットーである”Duty First”、最高の職務を果たしたと言えるでしょう。
オーストラリア陸軍M1956歩兵戦闘装備について

1960年代初頭、M1956歩兵戦闘装備を着用している1RAR(第1歩兵大隊)の某大尉。
オーストラリア陸軍は英連邦諸国が採用していたP1937歩兵戦闘装備を1960年代まで使用していました。
しかし、理想的とは呼べないP1937歩兵戦闘装備に代わり、アメリカ陸軍のM1956歩兵戦闘装備を採用しました。
同盟国であるアメリカと歩兵戦闘装備を共通することにより、補給面での簡素化も図られています。
形状や素材はアメリカ陸軍の仕様とは変わりませんが、オーストラリア陸軍向けのM1956歩兵戦闘装備は、USの代わりにD↑D※のスタンプが施されています。※DD(Department of Defence/国防総省の意)
バヨネットフロッグ(銃剣吊り)に関しては、オーストラリア陸軍での小銃用銃剣L1A2用に新規に生産されています。
M1956歩兵戦闘装備に装着出来るよう、ワイヤーフックが追加されています。
イギリス陸軍P1958歩兵戦闘装備について
イギリスで導入されたP1958歩兵戦闘装備はオーストラリア陸軍では採用しておりません。しかしながら1967年に1名の使用者(2RARの某少尉)の画像が残っていますが、氏がどのような経緯で入手したのかは残念ながら不明です。又、洋書では同装備を特殊部隊が着用しているイラストがありますが、こちらも出典は不明です。
後述しますが、P1937ベーシックポーチ/ラージをP1958キドニーポーチと誤認している方もいらっしゃるようです。
M1956歩兵戦闘装備の欠点とその現地改善
非常に先進的なM1956歩兵戦闘装備ではありますが、戦地で使用されるうちに欠点も見られるようになりました。
マガジンポーチはL1A1の弾倉を各2本が収納可能ではありましたが、より容量の多いP1937ベーシックポーチ/ラージ※を代替使用する兵士が少なからず現れました。画像の兵士の右腰に縛着されているのがP1937ベーシックポーチ/ラージです。7.62×51mm弾が100発程度は収納可能です。
※オーストラリア陸軍がかつて採用していた大型汎用ポーチ

シュラフ/寝具はクイックリリース可能なウェブストラップでサスペンダーに固定するようになっていましたが、密林内での携行性は悪く、また木の枝などでズタズタになってしまいました。
兵士たちはP1937ハーバーサック/ラージパックで携行するようになりましたが、拡張性の低い同パックはクイックリリース機能もなく、容量も余り多くありませんでした。
堅牢なM1956歩兵戦闘装備ではありましたが、過酷な戦場での消耗も著しく、前述の通りに代替装備(P1937やP1944)を使用する兵士たちも多く現れています。
マガジンポーチに付属している手榴弾携行用ストラップは信頼性が低く、専ら麻製のトグルロープ等の固定に使われています。
予備弾薬に関してはバンダリアで携行し、手榴弾はポーチ内に収納するよう励行されていたようです。
分隊支援火器の弾薬携行方法

分隊支援火器であるM60GPMGの弾薬携行手段として、エアマットレスを分解してカバーにするユニークな方法(兵士たちはBlow upと呼称)がとられました。
画像の兵士がたすき掛けしている黒っぽい物体がエアマットレスを分解したカバーです。重い弾薬箱を使用することなく、かつ弾薬を濡らすことなく携行する方法です。ベトナムに派遣された他国の軍隊でも同様の方法での携行は見られません。
ベトナム派遣オーストラリア軍についての四方山話
装備被服は同時代のアメリカ陸軍装備と比べて、入手することが困難になりました。
オーストラリア本国内でも消費されてしまった感もあります。
しかし、最近は映画用のレプリカ戦闘服等も製作されるようになりました。
日本国内では他国に比べてM1956装備の入手については比較的に容易です。
今回の展示品のような装備を再現することは不可能ではありません。
ベトナム派遣時のオーストラリア軍については、残念ながら邦訳された解説本などは殆どありません。
しかし資料が全く存在していない訳ではありません。
検索すれば画像は湯水の如く現れますし、情報開示された資料も当時のニュース映画も閲覧可能です。
各大隊別の写真集も販売されています。
当時の従軍者もご高齢でありますがSNSに勤しんでいます。
稀にコミュニティで昔話に花を咲かせる場合もあります。
そんなわけで、資料もモノも無い、なんて状況ではありません。
自分も、途中で何度か放置していた時期もありました。
でも、きちんと下調べしながら集めていれば、彼の国の方から「我が国でもここまでやっている人は少ないよ」なんて誉め言葉(リップサービスでしょうが)を貰えるまでになれるようにはなりました。
全ての軍装収集趣味について言えるのでしょうが、自分が着用している被服や装備が持つ意味を理解する必要がある、そんな気持ちがあれば、あまりにも適当な格好は出来ませんよね。
もしもベトナムに派遣されたオーストラリア軍について少しでも興味があった場合は、恐れることなくイベントで声をかけてみてください。
出典:Australian War Memorial
2023年02月16日
1964年頃のSF/CIDG/ARVN/AATTVの装備について
1964年頃のSF/CIDG/ARVN/AATTVの装備について。
※下の画像は1964年以前ですね…

※下の画像は1964年以前ですね…

戦闘装備はM1956LCEが基本となります。
M1956 Load Carrying Equipment参考サイト
※歩兵装備は正しい装着状況でないと本来の機能は発揮しません。翻訳して一読すると良いでしょう。"昔の装備は使い難い"と言う人が稀にいらっしゃいますが、適切な装備状態か確認してみてください。
年代設定は1964年です。M1967等の装備は使用できませんのでご注意ください。
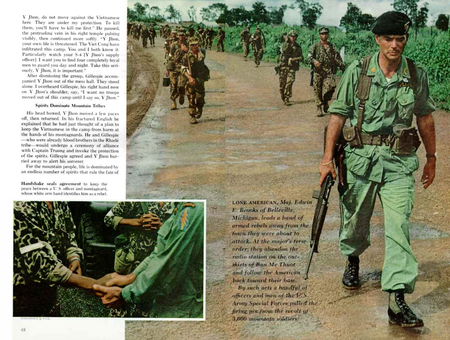
Eツール(携帯スコップ)やフィールドパック(バックパック)は省略しても問題ありません。
M1956以外の装備について。

ただし何でもかんでも組み合わせたり、使用はできませんのでご注意ください。
装備もリプロ推奨です。メーカーは問いませんが実用に耐えうる強度のモノを選びましょう。
安かろう悪かろうアイテムが混在していますので注意してください。
これらの装備はビクトリーショー等の物販イベント会場で購入すると良いでしょう。
ピストルベルト・水筒・アモポウチ・ファーストエイドポウチ
これらは必須装備とします。
特にファーストエイドポウチはデッドマーカーを収納する必要があります。水筒も状況中に水分補給の為、必須となります。
※状況を見ながら適時休憩は設けます。
背嚢・ラックサック・バックボード等について

RTO(無線手)、戦闘パトロール時を実施したい場合は使用制限はありません。
※エアソフトゲーム時には、これらに被弾した場合もヒット扱いとなります。
M1956装備については「知ってるつもり」の方も多いです。
今回はある程度まで許容しますが、厳密には使用できないようなモノもあります。現在の感覚で空いたスペースに装備を追加しないよう、心がけてください。
この機会に調べてみるのも良いかもしれません。
以下は参考サイトのリンクです。
M-1956 Load-Carrying Equipment
VietnamGear.com M1945 Load Carrying Equipment (Advisory Era)
VietnamGear.com M1956 Individual Equipment Belt


